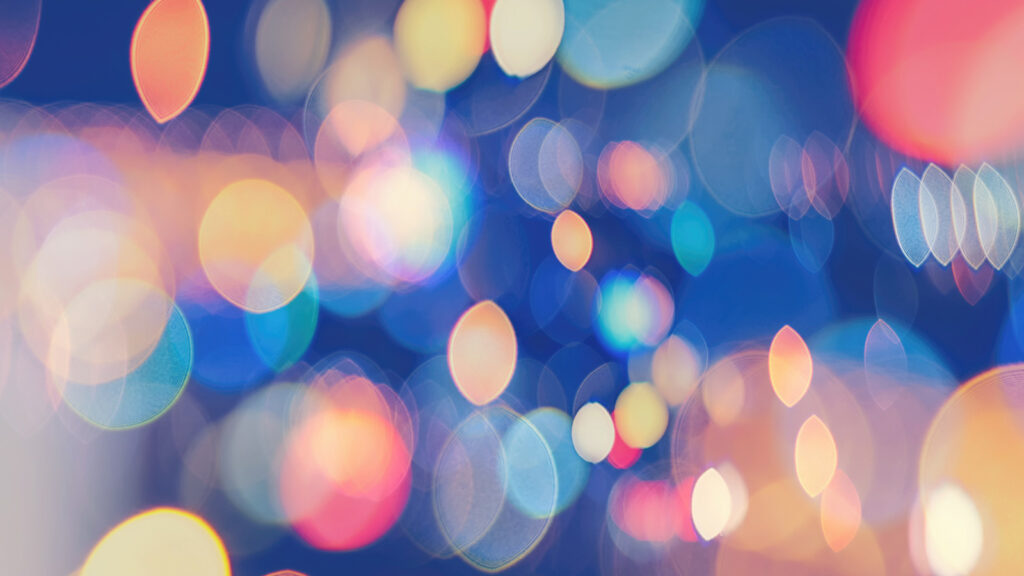公共施設と自宅をボーダーレス(borderless)にする
Photo : 京都 天龍寺の紅葉風景 / zheng qiang / stock.adobe.com
Posted by local knowledge on January 26th, 2024
公共(public)というのは案外面倒な言葉でして、単純に私(private)の対義語ですね、で片付けるわけにはいかない側面があります。「家族」でさえみんなが集まる公共空間としてのリビング(居間)とプライベート空間としての個室が区別されたりしますからね(もっとも日本は単身“世帯“が非常に多いのですが)。
公共性には、A:私的空間、B:触覚的に認知できる公共、C:視覚的に認知できる公共、D:公共政策における公共、というグラデーション(連続的変化)があるような気がします。私たちの生活空間として実感できる公共性はせいぜいCまでで、Dになると個々の多様性を吸収しきれませんから、他人事になってしまうのが普通でしょう。加えてB(触覚的公共)とC(視覚的公共)のあいだにも深い断絶があるような気もしますが(これを深掘りするとメディア論になってしまうので今回は割愛します)、いずれにしても公共(という概念)はかなり多層的である、とだけ押さえておくことにしましょう。
いわゆる「公共建築」にはこの多層性を吸収する義務があるはずですが、この時に大きな障壁になっているのが霞ヶ関の行政区分で、結果的に、保育園、幼稚園、学校、図書館、公民館、市役所、美術館、保健所、病院などが“境界をはっきりさせた”公共建築物として乱立してきました。人口増加前提の高度成長期にはそれでも良かったのかしれませんが、今回の能登半島地震で被害を受けた地域に限らず、日本の全ての市区町村では明確な境界(border)を有する公共建築はもはや不要でしょう。今後は境界を曖昧にしていくことでB(触覚的公共)、C(視覚的公共)、D(公共政策)がシームレスになっている状態を再現する建築が求められているはずです。渋谷の再開発のような「公共性・公益性を完全に無視した目を覆いたくなる開発」は東京だけにとどめておいていただきたい、というか東京はそもそもがっつり儲けたい人、一山当てたい人が集まった街ですから、経済効率(だけ)の最大化を目的にするのなら、渋谷・再開発は(ある意味では)模範的かもしれません。同時に、コミュニティや公共性を愛する人たちが棲むところではない、という意味では最先端の高層ビルはもっとも時代遅れの産物、最後の悪あがきにも見えます(同じ東京ではありますが、これと比較すると世田谷区・下北沢の低層前提の再開発はこれからの公共性の視覚化に(とりあえずは)成功しているように見えます)。
ところで、公共性に限らず、実は一つの建築物自体が多層的である、と説明しているのが「Stay hungry, Stay foolish」で有名なスチュワート・ブランド(Stewart Brand)の書籍、『HOW BUILDINGS LEARN-What happens after they’re built』です。この本の中で「建物は6つの層(S)でできている」と説明されていて、それは1:敷地(site)、2:構造(structure)、3:外装(skin)、4:設備(service)、5:空間設計(space plan)、6:家具調度品(stuff)、なのだそうです。無理やり6つのSを集めた感は否めないのですが、ここでは「この6つの層は変化の速度が異なるので、それぞれの時間的尺度に応じた解決策をとる必要がある」という重要な指摘が展開されています(建築家・秋山東一氏 のブログからの引用です)。 この層の境界が曖昧なのが日本家屋の特徴で、その象徴が「縁側」ですね。内(家族)の縁と、外(他人)の縁を繋ぐ、というのが縁側のミッションなのですが、木造軸組工法の最大の特徴はこの6S(特に、2と3、そして5ですね)自体を状況に応じて可変にできる、曖昧にしておく、という点にあるような気がします。
しかし今回の能登半島地震における多くの家屋の惨状を見ると、このような悠長なことも言ってられないわけで、今後の日本建築はどのように作っていくべきか、を真剣に考える必要がありそうです。そのヒントの一つとして、建築が量産という概念と出合った20世紀に針を戻して、二人の工業先進国アメリカの巨人、バックミンスター・フラーとチャールズ・イームズが仕掛けた挑戦を分析してみよう、というのが来週のローカルナレッジ「住宅をつくる人々の新しい物語(第2回)20世紀を見逃すな(松村秀一氏)」です。ぜひご参加ください。
ローカルナレッジ 発行人:竹田茂
ニュースレターのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。
最新のコラムはニュースレターでお送りしています。お申し込みは下記から
ニューズレター登録はこちら