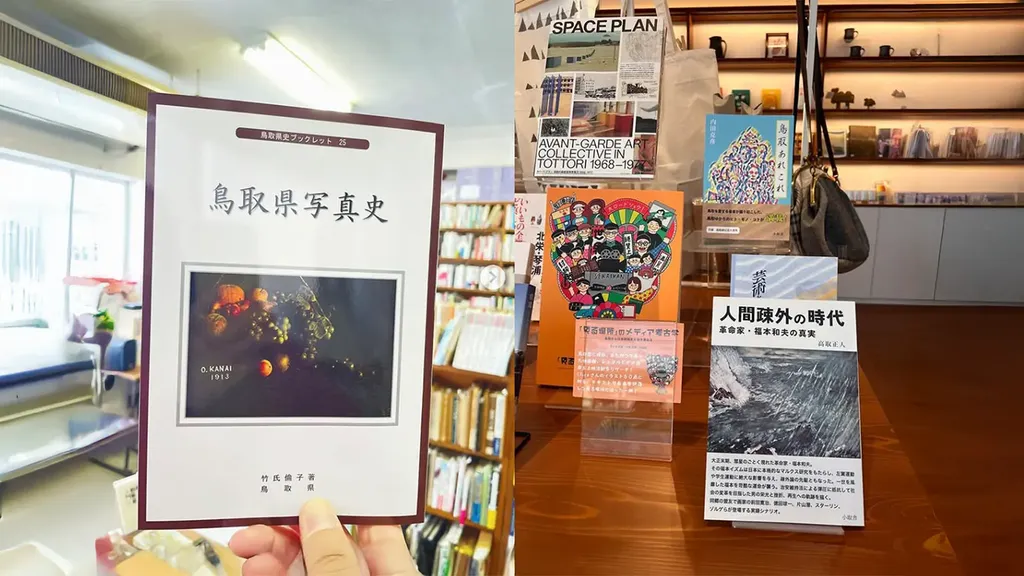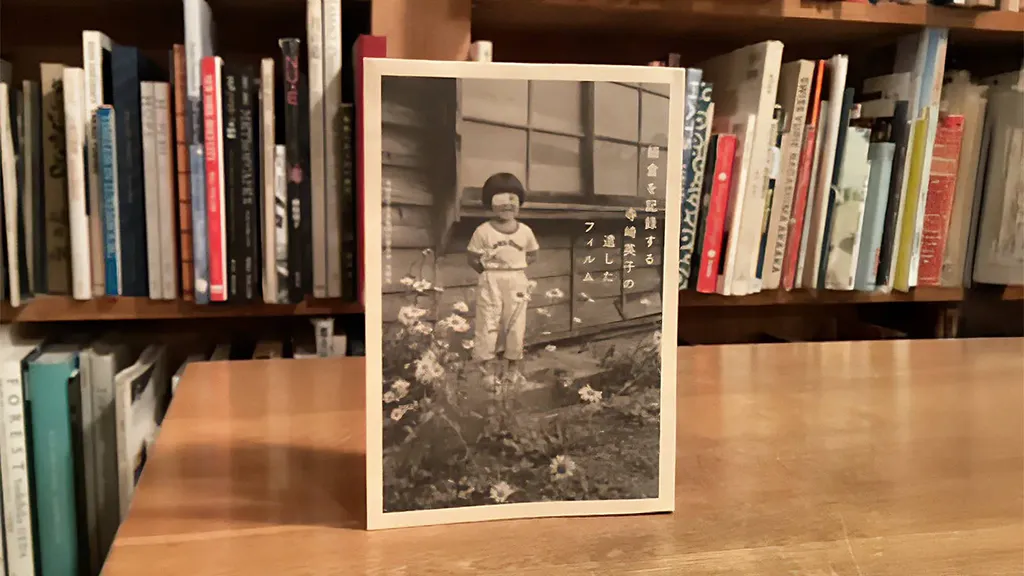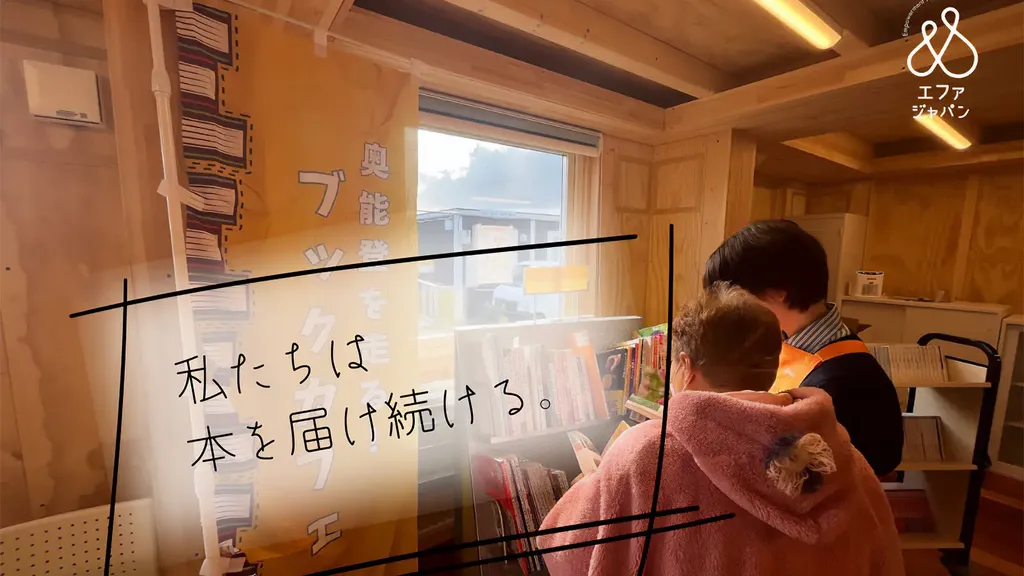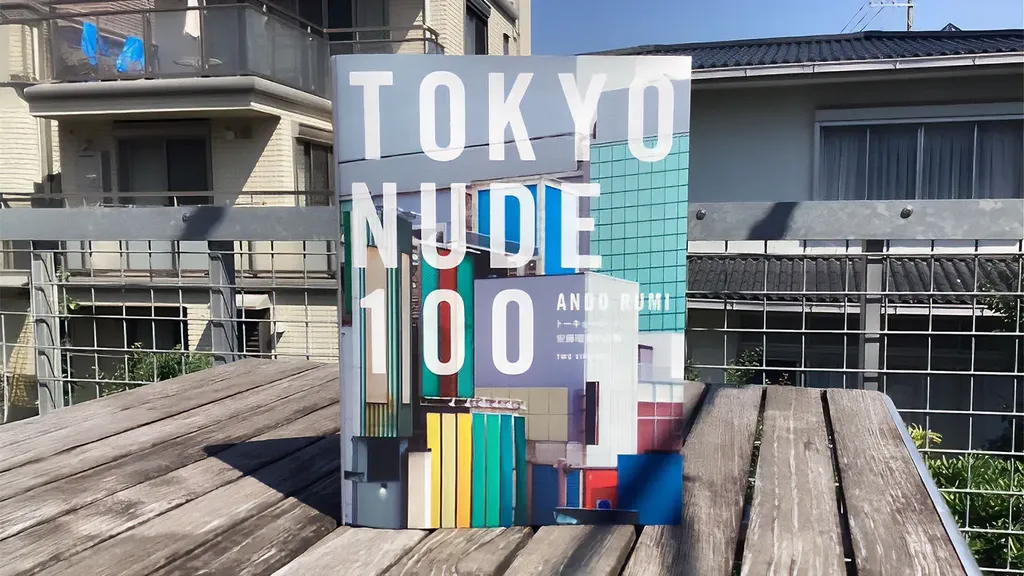- ニューズレターNewsletters
- 書籍一覧Books
- 人文学Humanities
- 社会科学Social Science
- 自然科学Natural Science
- 複合領域Interdisciplinary
- 村上塾Murakami Yoichiro
- 島薗塾Shimazono Susumu
- 松村秀一建築塾Architecture and Building Construction
- 京都大学学術出版会Kyoto University Press
- 本の場Where Books are Activated
- シュレディンガーの水曜日Schrödinger's Wednesday
- 名古屋外国語大学出版会Nagoya University of Foreign Studies Press
- 未来のメディアの作り方Media and Communication Studies
- 地域人による地域創生living in the local and revitalizing the local
- 写真集の夜Shashinshu-no-Yoru
- 縁側ラジオEngawa-Radio
- ローカルナレッジ ミートアップLocal Knowledge MeetUp
左のメニューをマウスオーバーすると概要文が表示されます