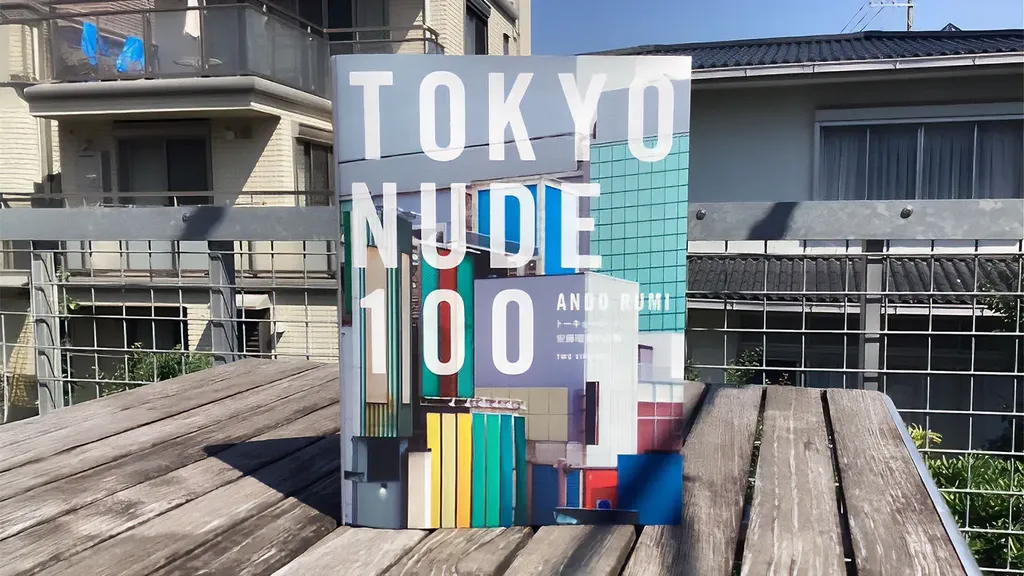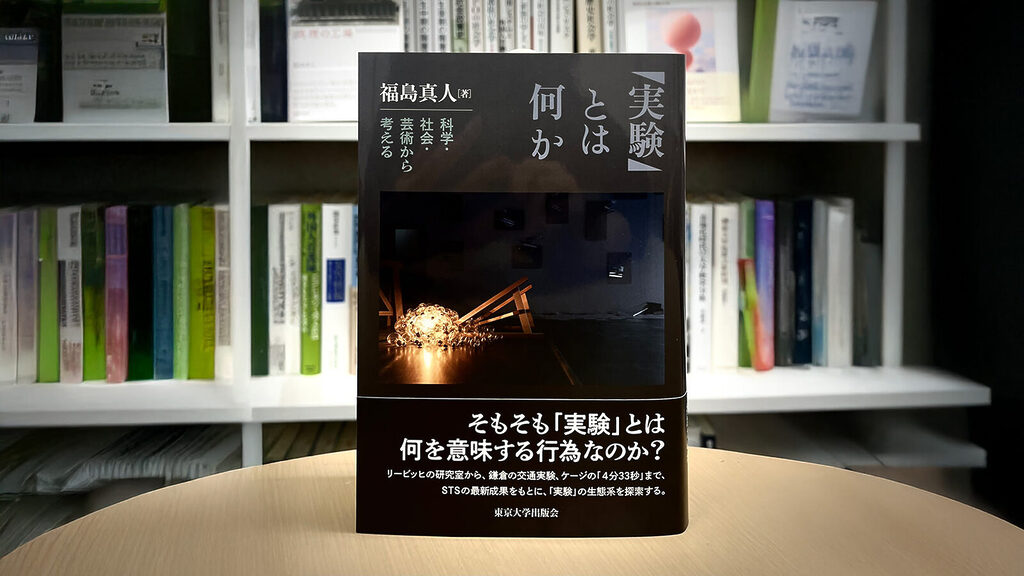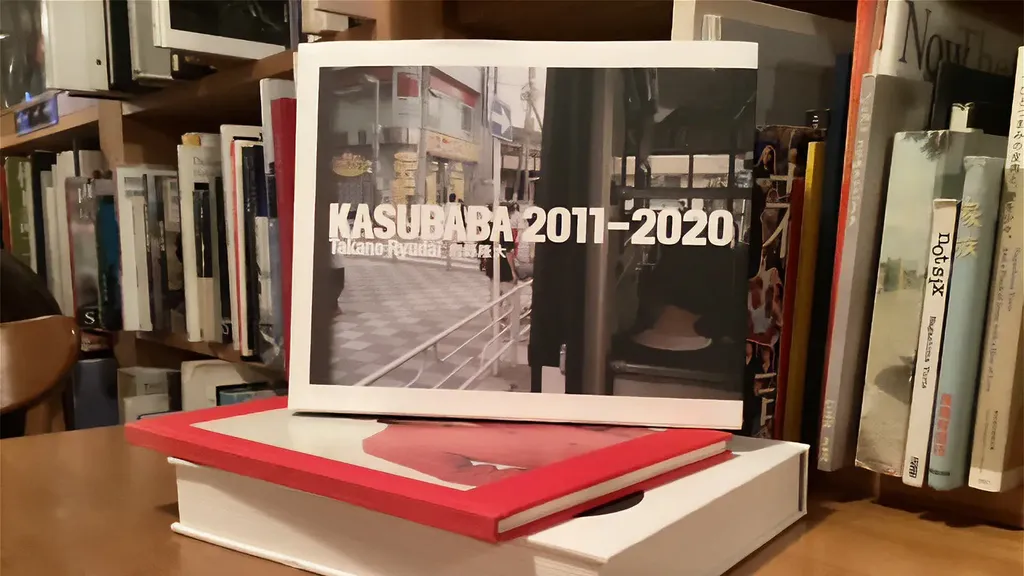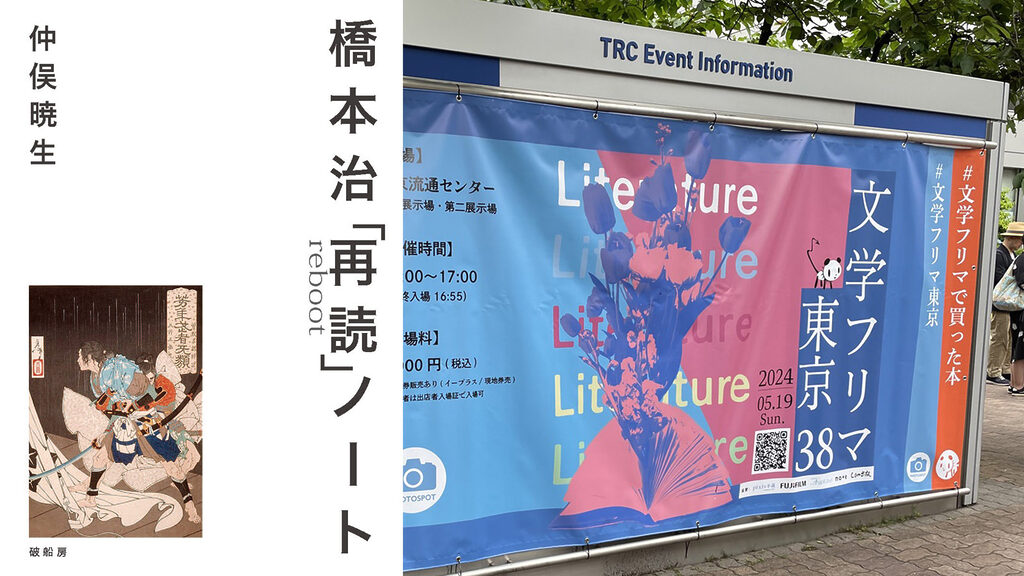地域の知的ベースキャンプとしての図書館と書店
3rd Place with Books
米国の社会学者レイ・オルデンバーグ(Ray Oldenburg)が、著書『The Great Good Place』でサードプレイス(3rd Place:職場でも自宅でもない、寛げる第3の場所)の重要性を指摘したのは1989年。彼の主張自体はジェイン・ジェイコブズ(Jane Jacobs)の『アメリカ大都市の死と生』(1961)を下地にしていて、都市化が進行していく中で、インフォーマルでお気軽な社交の場が失われ、家庭や職場以外でのコミュニケーションが喪失されていることを嘆くものでした。さて、少子高齢化で低成長を余儀なくされている日本の各地域がこれから作るべきサードプレイスとはいかなるものでしょう。喫茶店・居酒屋・公民館などのように機能主義的に細分化・先鋭化した施設ではなく、図書館や書店などの本のある場所において、非公式なコミュニケーションが自然発生する仕組みがインストールされた場所こそがサードプレイスに相応しいのではないでしょうか。ここで重要なのは「目的の曖昧さと空間的多様性」です。先達の事例に学びながら、自分の地域に応用可能かどうかを検証していきましょう。