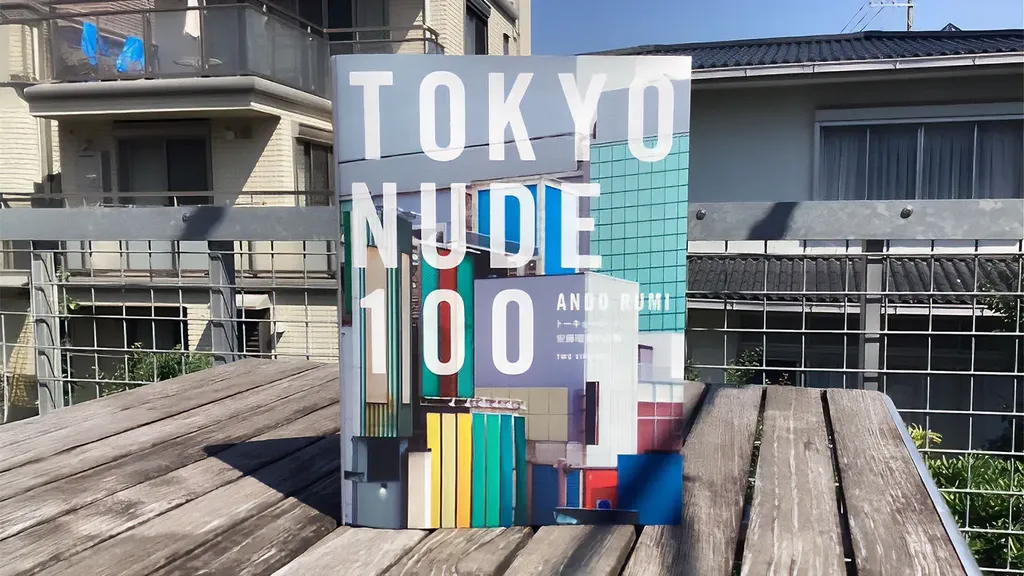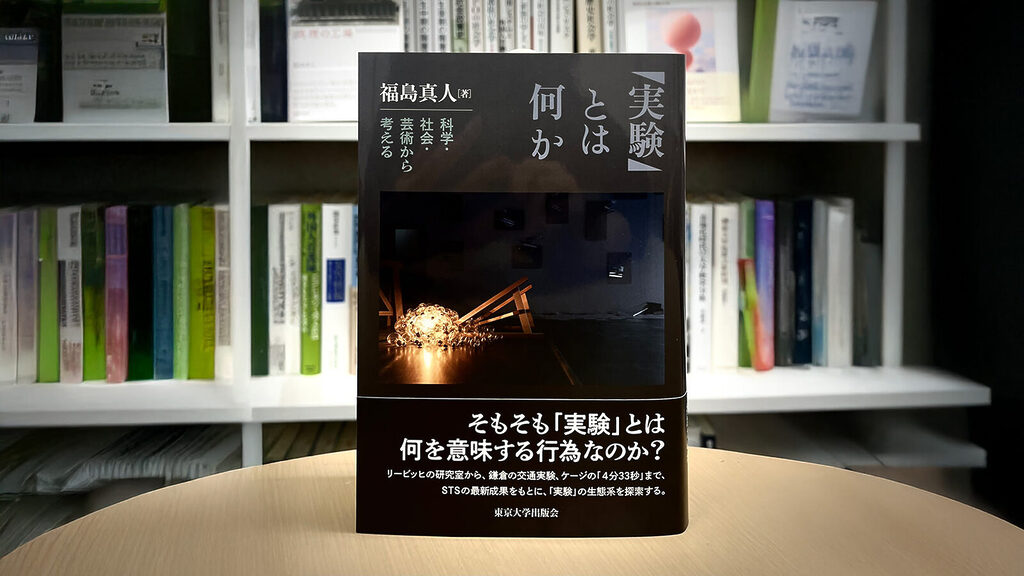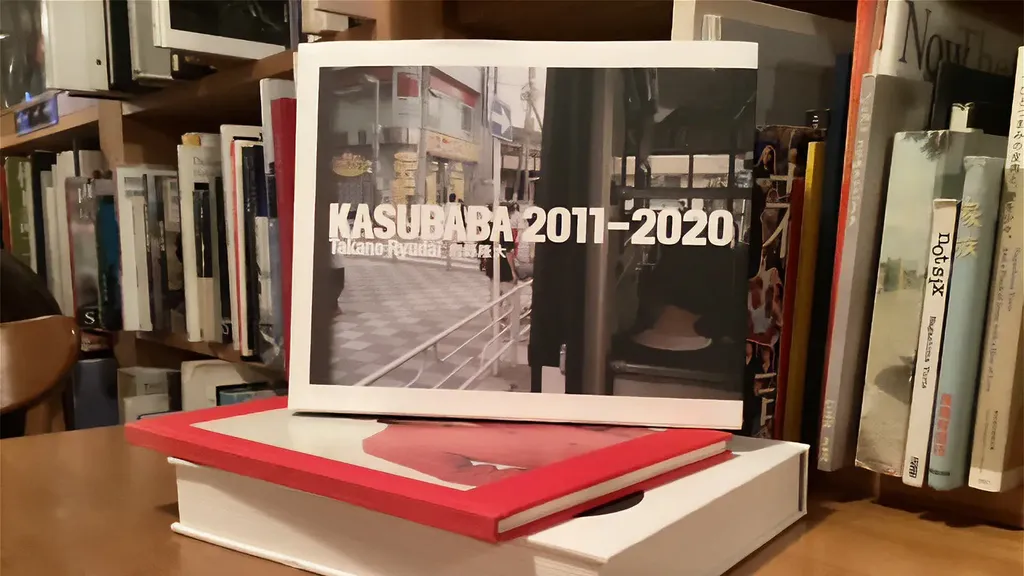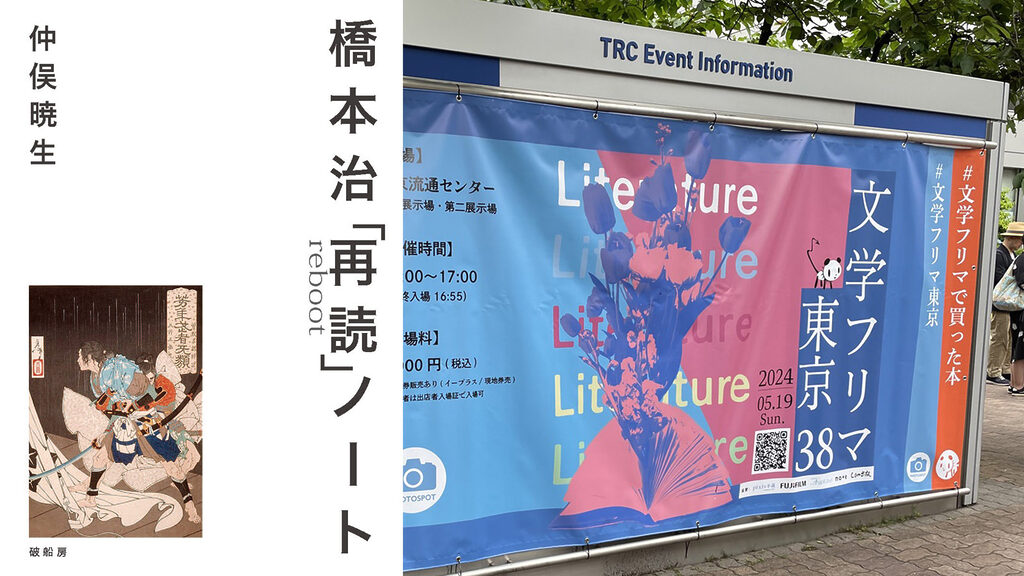人文学
Humanities
人文学(じんぶんがく)は、人間が生み出す文化やその価値を考察・研究する学問分野です。哲学・文学・文化人類学・歴史学・宗教学・言語学・美学などが代表的でしょうか。さまざまな事象がデジタル化される現代において、実は今、その実力が最も見直されている分野でもあります。例えばビッグデータ解析や大規模言語モデル(LLM)での新しい価値創造は困難ですが、エスノグラフィー(ethnography)調査からは、さまざまな人類の創造的未来が予見できます。一方、人文学がデジタルテクノロジーを補助的に利用することで、その研究が加速されるという現象が出現しつつあるということにも着目しておきましょう。詩人の荒川洋治氏が主張するように『文学は実学である』なのです。