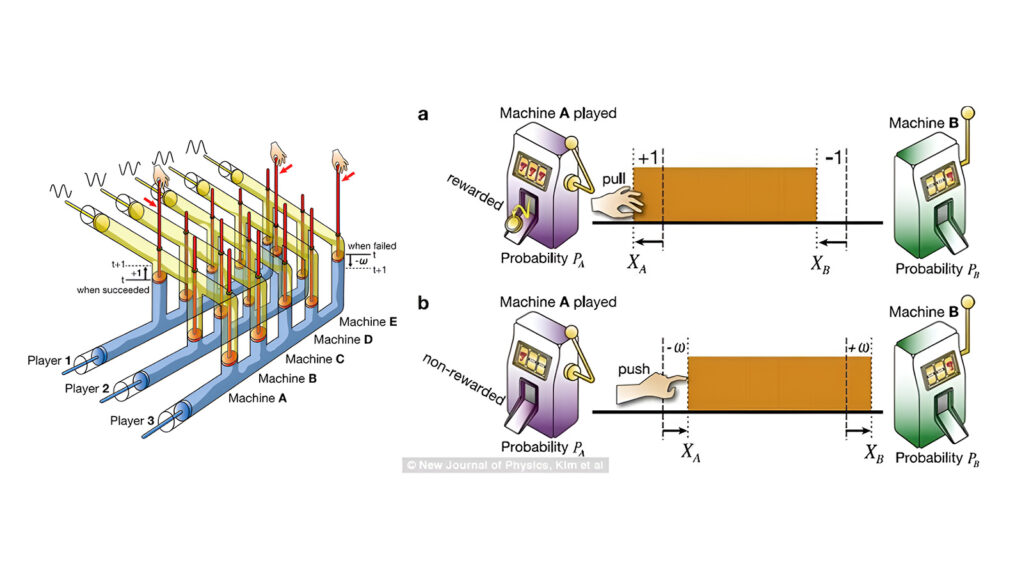複合領域
Interdisciplinary
「学際的」とは,本来、ある学問の専門領域とそれに隣接する他の領域の間に存 在する中間領域を意味する言葉ですが、現在の学際研究ではある特定の問題について様々な領域の研究者が集結する、もしくは一人の研究者が複数の領域を同時に研究するということが増えました。古代ギリシャの数学・哲学から始まった学問は近代化に歩調を合わせる形で細分化を繰り返してきましたが、行き過ぎた細分化が学際を誕生させると同時に複合領域が見直され始めた、と考えられます。これは細分化された学問が実は全て横(ヨコ)でつながっていて、特定領域の専門家であることを自覚している研究者にも積極的な他領域への往復運動が求められていることを示唆します。研究者のみならず、実業の世界、あるいは地域活動においても求められているメンタリティだと言えるでしょう。